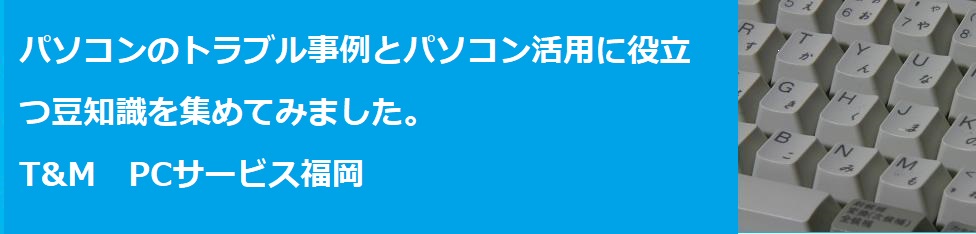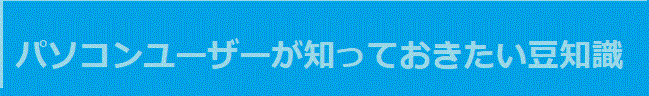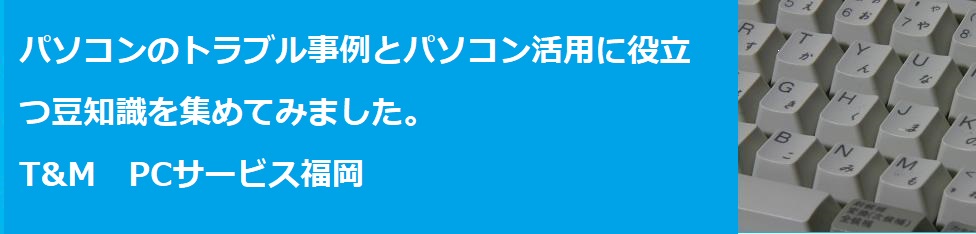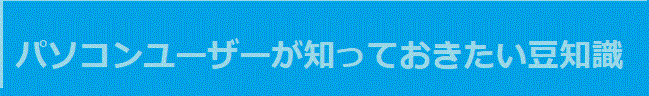世界の終わり方その1 第2話
翌朝、研究室に入ると僕のゼミの学生が二人来ていて、昨日のUFOの話で盛り上がっていた。
ここで少しだけ自己紹介をしておこう。
僕は大学の理学部で准教授をしている。
准教授というのはAssociate Professorの訳語で、教授に次ぐ職階のことである。
以前は助教授と呼ばれていた。
仕事の中身は微妙に違う。
僕に気がついた結城君に
「先生、お早うございます。先生は昨日のUFOを見ましたか」
といきなり声をかけられたのだが無視して荷物を机の上に置いた。
もう一人の学生である水原さんが話し始めた。
「私も見たんですけど、あのUFOって変ですよね、だって誰もあれが空を飛んでくるところを見てないんですよ」
「光学迷彩って奴じゃないか」と答えた。
「プレデターですか」
「うん、007のボンド・カーにも使われていただろう」
「知りません」と水原さんは答えた。
「あれはSFじゃないから仕方ないかな、君はあんな映画は見ないだろう」
光学迷彩というのは要するに周りから視覚的に見えないようにしてしまう技術の総称だがSFの世界では普通に使われているようだ。現実の世界では東大や、マサチューセッツ工科大学などで研究が行われているらしい。しかし、まだ実用化には時間がかかると思われる。
「話に割り込んで申し訳ないんですが先生、他にもおかしな所があるような気がするんですけど」
と結城君がいう。
「僕もそう思っているよ。おかしな所だらけだ。ニュースでは宇宙人とのファーストコンタクトだなんていってるようだが納得できるわけはないだろう」
「君がおかしいと感じた点をはなしてみなさい」
「先生は宇宙人とテレパシーで交信したんでしょう。何か変わった点に気がつきませんでしたか?」
「何で君がそんなことを知っているんだ。いや確かに宇宙人の声と思われるものが頭の中に聞こえたんだが、でもあれは僕に呼びかけたんじゃなくて、いわゆる一斉同報、つまり、放送みたいなものだったと思う」
「それに僕は答えようとしたわけではない。単に頭の中で考えただけで誰かに向かって会話をしようとしたわけではないんだ。宇宙人も僕の思考に反応したのだとは限らないと思う」
いや、確かにおかしい、僕は本物のテレパシーがどんなものかを知らない。
僕が知っているテレパシーというのは子供の時に見たテレビ映画の「電撃スパイ作戦」の中で登場人物のスパイ3人が会話をするときに使うあれだけだ。
大体、テレパシーといえども通信を行うときはあらかじめ双方で手順を決めてなければ無意味なはずだ。
その上、全く異質な環境で進化したはずの宇宙人といきなり会話ができるはずがない。
あのときはテレパシーだと思ったのだが実際にはあらかじめ準備された博多弁を利用した放送だったのではなかろうか。
それにしても何で結城君は知っているんだろう。
「先生は思考波というものの存在を聞いたことはないですか?」
「答える前に僕の方から質問がある。君はSFを読んだことはないのか」
「ありません。子供の時から勉強ばかりでそんなことに興味を持つ暇はありませんでした」
「なるほどそれでこの僕にたいしてそんなつまらない質問をするんだな」
文部科学省は子供たちに夏休みの宿題としてSFの読書感想文を提出させるべきだと思う。
「水原君、思考波というのがどんなものか、結城君に教えてやってくれ」
僕の前にコーヒーの入ったカップを置きながら水原君は言った。
「先生、いいんですか、私が説明しても?」
「ああ、もちろんかまわない」
「結城君、SFの世界では思考波というのは精神活動を行うすべての生命体が放射している波動の一種で、電磁波や重力波と同じように、到達距離は無限大なの、でも光子や重力子のような粒子を伴わない純粋な波動なので相対論や、量子力学の制限に従っていないわけね」
「水原君ありがとう、すまないが後は僕が説明しよう」
・・・先生どうしたのかしら、私に説明しろといったくせに、結城君だって理学部の学生なんだからこれぐらい理解できるはずだわ・・・
「思考波というのは媒体に通常空間や、亜空間を利用していて、亜空間を利用するときだけ我々の宇宙全体に超光速で情報やエネルギーを伝達する場合があるわけだ」
「でも僕が以前から疑問に思っていることは例え思考波という特殊な波動を利用していても必ずしも意志が伝わるわけではないということだ」
「電話という機械を考えてみれば分かることだが相手が外国人だったらいくら電話が正常に動いていても会話自体は意味不明ということが起きるわけだ」
「だから僕はこの宇宙でテレパシーが思考波を利用しているとすれば会話をしている両者の間に、高性能のコンピュータか高度の知能を持つ生物の翻訳者が介在していると思っているわけだ」
「いや、すまない確かSFの設定の話だったな」
突然、机の上の電話が鳴り始めた。
「先生、N大学の大崎先生がお見えです」
「あぁ、先生は僕の部屋を知っていらっしゃるからあがってくるように伝えてください」
「君たちは大崎先生を知っているだろう」
「はい」
「大崎先生はここ半年余りの間、海洋調査船で南氷洋まで行かれていて3日前に日本に戻ってこられたんだ。海洋に浮かんでいるゴミの調査をされているんだが何か変わった不思議なものを見つけたらしい」
「昨日、大崎先生から知らせが入っていたんだが今日はその不思議なものについて僕の意見を聞きたいといって会いに来られたんだ」
「君たちもこの部屋にいなさい。もし先生の了解が得られたら、僕と一緒に見せてもらおう」
部屋に入ってきた大崎先生は満面に笑みをたたえつつ、開口一番
「一ノ谷博士、久しぶり、ナメゴンの卵を持ってきたぞ」
といった。
「やめてください、今時の学生には何のことか分かりませんよ。それにしても相変わらず元気そうですね」
「おや、お久しぶり、君たちも僕のおかしな話を聞くために集まってくれたのかな?」
大崎先生はまじめな顔つきに変わって
「あまりにも奇妙な話なんだが、君たちの意見も聞かせてもらいたい」
といった。
「これまでの調査した記録をDVDに入れてきたんだがどうしたらいいかな?」
「そこにパソコンがありますから使ってください。」
「ありがとう、まず先に、僕の調査の目的とここに来るまで調べた内容を一通り説明しておこう」
「僕は海洋に浮遊しているプラスチックのゴミが生物に与える影響について調査するために北太平洋から南氷洋までに生息している動物プランクトンと微少なプラスチックゴミを収集してきた」
「この調査を行う動機になったのは最近アメリカで行われた海洋調査の結果と報告だ」
「それによると採取されたプランクトンは450グラムだったのに対して、プラスチック片は2,700グラムあったということだ」 (これは恐るべき事実です。作者註)
プラスチックごみは鳥や、海洋の生物が飲み込んで、死ぬ原因になるし(例えばウミガメがビニールの袋をクラゲと間違えて飲み込んでしまう)、微少なプラスチックごみの場合は動物プランクトンが植物プランクトンと間違えて食べてしまうことがある。
このプラスチック片には内分泌攪乱作用が疑われている化学物質が付着している可能性があるし、これが原因で南氷洋に生息しているオキアミの一種が最近激減している可能性があるらしい。(もちろん、他にも色々な原因があると思われている。学者は検証してみないことには納得しない。これは当然なことである。 作者註)
「そのように考えられる理由があるので、南氷洋の各所で、オキアミを採集したのだがこの中に僕の頭では理解できないものが混じっていたのだよ」
採集されたオキアミを生きたままで保存したかったので、とりあえず調査船の水槽に入れた。
つぎにこの中の一部を他の水槽に分けて植物プランクトンと同じ程度の大きさを持つプラスチックの粒子を与えてみた。
するとこれを食べた大部分のオキアミたちは死んでしまったのだが、生き残った残りの一部が他のオキアミを攻撃し始めた。
攻撃されたオキアミがばたばた死んでいくので、共食いを始めたのだと思って大急ぎで、生き残っていたオキアミを掬って別の水槽に分けたわけだが、これがとんでもない連中だった。
もちろん、詳しい調査は今からなんだがそれでも、出来る範囲では調べてみた。
「その結果を今から見てもらおう」
大崎先生はプラスチックのケースをバッグから取り出してみんなに見せた。
それには何かの結晶と思われる物質が入っていた。
しばらく眺めていた僕たちは「先生これは一体なんでしょう」と訪ねた。
大崎先生は驚くべきことを語り始めた。
「これはね、オキアミだよ」
「いや、元はオキアミだったと言うべきだな」
「こいつ等は水槽からすくい上げられると数秒もしないうちにこの結晶に変化してしまったのだよ」
「この中の一つを水槽に戻してみたが海水に溶けてしまってそれきりだった。まるで元のオキアミが正体を知られるのをいやがっているみたいだった。」
「この結晶体をいくつか置いていくから君の所でも、詳しく調べてみてくれたまえ」
「ところで君たち、この奇妙な出来事をどう考えるかね?」
「先生、これはこの奇妙なオキアミが海水から空気中に出されたことによって死に、死骸が結晶化したと言うことなんでしょうか」
「水原君、最初は僕もそう思った、でもあまりに変化が早すぎる気がする」
「僕はこんな生物は見たことがない」
「まるで、殺された宇宙人が正体を現しながら溶けていくのに似たような気がしたな」
「先生、そうするとこれはどこか他の世界から来た生物ではないかとおっしゃるんですか」
「いや、見たことがないと言っているだけでそこまで飛躍した結論を考えているわけではない、結城君はどう考えるかね」
「僕はSFは苦手なんです。どこかの国がこんなものつくったのかもしれないとは思うのですがどんな利益があるんですかね」
「大崎先生、ここには物質の検出装置があるので、とりあえずこの結晶の組成を調べてみましょう」
「しばらく時間がかかりますのでその間みんなで食事に出ませんか、X線を使った構造解析もその間にできるかもしれませんよ」
大崎先生はその考えに同意され、いったんホテルに荷物を預けて近くの中華飯店に集まることになった。
「学生諸君、今日は僕のおごりだから遠慮しないようにな」といって大崎先生は帰っていった。
それが大崎先生の元気な姿を見た最後であった。
このページのトップへ
豆知識の目次へ